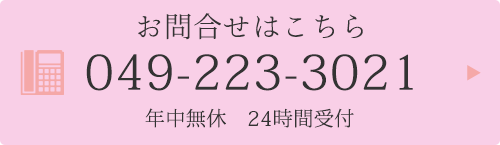ご葬儀の流れ
事前相談
ご葬儀前の事前相談も承っております。
急なことなので落ち着いて考えるまもなくご葬儀を迎えることになってしまいます。
先に考えることを後ろめたく考えられるかも知れませんが、大切な方を送る儀式です。
心残りが無いよう、後々悔やまないように相談しておくことにより、心にゆとりをもたれ、納得の行くご葬儀で故人を送って差し上げることになるでしょう。
▼
ご臨終
ご遺体に触れず、直ちに医師、または警察へ連絡をしてください。
- 急死の場合
直ちに医師を呼ぶ→医師より、死亡診断書を発行していただきます。
医師がわからなければ110番します。警察が来て検死が行われます。 - 自宅以外での即死の場合
事故死、自殺、他殺を問わず、警察に通報します。検死が済むまでは手に触れてはいけません。
▼
お電話ください

当社への連絡 049-223-3021
▼
お迎え

専用寝台自動車にて、弊社がお迎えにあがります。
- 病院で亡くなられた場合
病院からご自宅まで搬送者の手配を承ります。病院を出発できる時間にお迎えに参ります。
▼
ご安置

ご自宅に安置いたします。(お預かり可能です。)
釈迦様が亡くなられたご様子が「頭北面荷西右脇臥」、すなわち北枕だったのでそれに基づいて亡くなった方を北枕にします。
安置した後、枕元に枕飾りをいたします。白木の台、もしくは白い布を掛けた木机の上に、1本の線香(中心)、1本のローソク(右側)、1本のしきみ、又は1本の花(左側)、鈴を右手前、枕飯は線香後方中心、右横に団子(25個)、左にコップに水入れて飾る。ただし、枕飾りはすべて揃えなくてはならないと言う事はなく、枕団子は略されることがあります。ローソクと線香だけは途絶えることのないよう、灯し続けてください。
▼
葬儀の打合せ・準備

①誰を喪主にするかを決める
②葬儀の日取りを決める
③関係者へ葬儀の連絡
④遺影写真準備
※なるべく最近のもので、故人の気に入ったものが良いでしょう。
他人任せにしないで是非とも遺族で選んでほしいと思います。
以下、葬儀にかかわるすべての手配準備を当社にて行います。
- 役所の届出等の代行
- 見積りスケジュールの作成
- 式場、火葬場、霊柩車の手配
- 引き出物、お料理の手配
- 供花の手配(会社関係の供花の手配も行います。)
▼
納棺
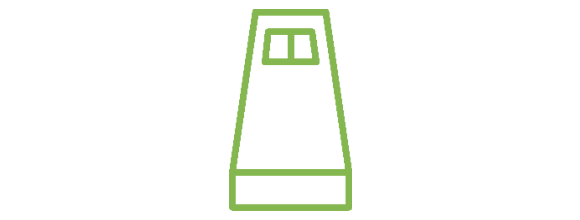
湯灌の後、お化粧をし、装束を着せ納棺いたします。
本来は経帷子を着せた故人に白木綿の手甲、脚絆をつけ手に数珠、杖、足は白足袋で草鞋ばき、胸に頭陀袋を提げ、頭に三角の布をつけて寝かせます。現在は湯灌の後、着物の上からこれらを揃えて入れるのが一般的です。棺の下には白い薄い布団を敷き、枕をおきます。
手を合掌させ、ドライアイスを置きます。胸に守り刀を乗せます。
納棺は出来る限り、近親者の手で行いましょう。
▼
通夜
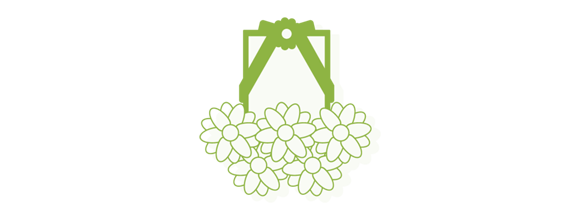
祭壇、式場設営を行います。
≪花飾りの置き方≫
祭壇の左右の花飾りは内側が上位となり、祭壇に向かい左、右の位になります。
屋外でも入り口より左上位となります。
開式:読経→焼香→通夜ぶるまい
≪喪主挨拶例≫
(御礼)
本日は、お忙しい中を父・○○○○の通夜にお運びくださいまして、ありがとうございます。
亡き○○が賜りました数々の御厚誼に対しましても本人に成り代わりまして心から御礼申し上げます。
(死の報告)
○○は、一昨日の午前○時○○分に、○○の為、○○病院で他界いたしました。享年○○歳でした。
(心境)
○○が穏やかな最期を迎えることが出来たのは、皆様から温かいお励ましをいただいたお陰だと存じます。
改めて皆様に感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
(案内)
尚、葬儀・告別式は明日○月○○日○時より当齋場にて行うことになっております。よろしくお願いいたします。
(結び)
では、ささやかながらお食事の用意をいたしましたので、故人をしのびながらお召し上がり下さい。
本日は誠にありがとうございました。
▼
葬儀
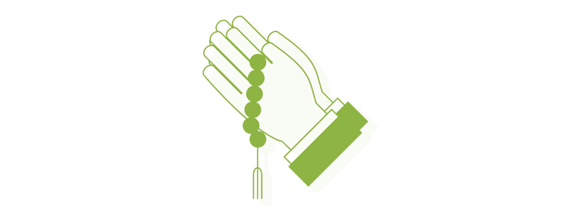
開式→読教→焼香→弔辞→弔電→遺族・親族とのお別れ→ご挨拶→出棺(花入れを行う)
≪会葬への御礼挨拶≫
私は、故○○○○の長男で○○○○と申します。喪主として一言ご挨拶申し上げます。
本日は、お忙しい中、亡き父の葬儀に、多数ご参列下さいまして誠に有難うございました。
お陰様で滞りなく式を済ませました。
父は、一昨日入院先の○○病院で○○時○分に、家族に看取られての静かな最後でした。満○○歳でした。
父の存命中は皆様には何かとお世話になり、遺族として、深く感謝いたしております。特に入院中は大勢の方に見舞っていただき、父もどんなにか元気付けられたかしれません。故人に成り代わりまして心から御礼申し上げます。
父亡き後も私ども遺族に対し、変わらぬご助力を賜りますようお願いもうしあげ、簡単では御座いますが挨拶とさせていただきます。
本日は最後までお見送り下さいまして、有難うございました。
▼
火葬

収骨は近親者で行います。
▼
精進落とし

ここまででひと通りの儀式の終了です。
精進落しの料理等は専門仕出店等ご案内いたします。
▼
初七日法要

近年は告別式中に行うことが多い。ご住職様と、ご相談の上お決めしたいと思います。
▼
後飾り
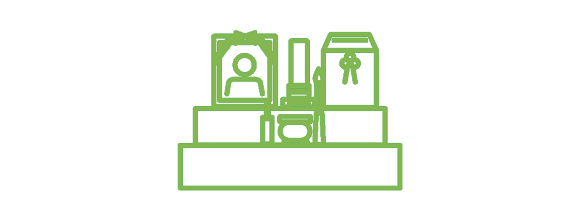
葬儀後ご家庭に後飾り祭壇を設置いたします。
▼
四十九日法要

日時を決め僧侶へ依頼、納骨します。後返しの場合49日に忌明け挨拶状をつけて香典返しを行います。
初七日から、49日までに行われる、追善供養は内輪だけで済ませますが、49日法要を盛大に行うのは、この日が最後の審判が行われる日で死者の魂が極楽へ行かれるかどうか、決定される日である為、遺族、親戚、知人などが集まって皆で成仏を願おうと言うことです。